2025年7月。
日本は参議院選挙を迎え、介護・福祉業界も介護保険制度のあり方や介護報酬、賃上げの行方を見守る上で関心の高いものとなっています。
一方で2025年4月には1000人を超える「財務省解体デモ」が行われ、消費税のあり方が問われているのも事実です。
こうした背景がある今、介護・福祉従事者個人もまた自分の働き方を見つめ直す時期に差し掛かっています。
そこで今回は2025年の現状を踏まえつつ、介護・福祉従事者にとって独自の収入源となる副業について考えていきます。
副業の前に押さえておきたい、介護・福祉に関わる社会情勢
副業を考える前にまず押さえておきたいのは、先の「財務省解体デモと介護・福祉業界は『社会保障費』でつながっている」という点です。
一般に社会保障費の財源は国の予算の「一般会計」にあたり、その財源となる歳入には所得税や法人税、公債金の他に消費税も含まれます。仮に消費税が減税あるいは廃止となれば、その分の予算は他から用意するか、あるいは社会保障費自体を縮小することにもなるでしょう。
こうしたお金の流れを受けて自民党の森山裕幹事長は「消費税を守り抜く」と発言しましたが、生活困窮にあえぐ国民感情に適わず物議を醸しています。
また消費税に関して、財務省の解説によると
「平成26年度以降、消費税の税収は、社会保障4経費(年金、介護、医療、子ども・子育て支援)に充てることになっています。」
とありますから、その用途は概ね社会のために使われていると言えます。
一方で消費税の用途のうち、輸出還付金に関しては上記に当てはまるものではなく、輸出によって回収できない消費税の先払い分を後から還付されるお金となっています。
例えばAという輸出企業が下請けのBという国内企業に受注した製品の代金を払うとき、AはBが支払う消費税込みの代金を支払います。Bは売上のうち消費税分を国に納めることになります。
Aの輸出品は海外で消費されるため、本来消費税は掛かりませんし免税対象となります。しかしBには先に消費税を支払っているためその分マイナスとなってしまいますから、輸出還付金によって先払いした分を還付してもらう訳です。
つまりAは免税対象の輸出品で得た売り上げには消費税が掛からず、さらに下請けのBに支払ったとされる消費税分が還付されることとなります。
仮に輸出品の価格を「Bに支払った消費税分上乗せ」して海外で売れば消費税分は取り戻せますし、「Bに支払った分の消費税分」は輸出還付金として戻ってくるという話にもなります。
この輸出還付金を「消費者が負担し」「事業者が納税した」消費税から支払っているのは問題ではないか、と主張する動きも見られます。消費税が本来の用途以外に使われており、一部輸出企業の懐を暖めているだけではないか、と。
こうした世の流れを受けた上で、介護保険制度や介護報酬、介護職の賃上げを望むとなれば「消費税増税の名目」を国に与えることとなり、国民の意思に反する流れに加担する可能性すらあり得ます。
そうなると、賃上げや介護報酬増額を望むのは真に『福祉』(人のしあわせ、ゆたかさ)たり得るのか。
国のお金の使い方に疑問を持ち始める方が増える中で、時代と逆行するかのような方針、行動を取ってはいないでしょうか。
そう考えるだけでも、「せめて自分の問題くらいは自分で解決しよう」と考え、その問題の中でお金が足りないのであれば副業をして賄うのも一つの選択肢だと言えます。
副業を行う上での基本的な情報
「自分のお金の問題を自分で解決しよう」と副業を始めるときに、注意すべき点があります。
SHARED OFFICE BIZ comfortによれば、副業の注意点には大きく分けて「準備期」と「副業開始後」の二つがあり、それぞれ
【準備期】
・就業規則の確認
・本業に影響が出ない副業選び
・副業の所得区分の確認
・社会保険加入の有無
【副業開始後】
・本業に支障を出さない
・確定申告の必要性
・翌年の住民税に備える
といった点が挙げられています。
他にも「副業のためにした方がよいこと」がまとめられており、上記内容を含めた詳細を知りたい方は下記リンクよりご確認ください。
介護の副業、その実情は
では、介護の副業、その実情はどのようになっているのでしょうか。
厚生労働省「副業・兼業に係る実態把握の内容等について(2020年)」によれば、副業の実情は以下の通りとなっています。
副業をしている人の割合は全体で9.7%であり、本業の就業形態別では、「自由業・フリーランス(独立)・個人請負」が29.8%と最も高く、「正社員」が5.9%と最も低かった。
本業の業種別では「農林漁業・鉱業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス、娯楽業」、「教育・学習支援業」、「医療・福祉」、「その他のサービス業(理容業など)」、「その他」が、全体と比べて割合が高かった。
本業の収入別では、「5万円未満」、「5万円以上10万円未満」、「10万円以上20万円未満」、「70万円以上」が、全体と比べて割合が高かった。
これらから
「副業をしている人はまだ多いとは言えないが、医療・福祉分野でも副業は進められている」
「副業を始めることで多くの人が月5〜10万ほど収入を得ている」
と言うことができます。
副業を行う理由としては
・副業をしている理由について、全ての就業形態で「収入を増やしたいから」との回答が3割を超えていた。
・「会社役員」を除く全ての就業形態で、「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」との回答が3割を超えていた。
• その他、「臨時・日産社員」は「働くことができる時間帯に制約があり、1つの仕事で生活を営めるような収入を得られる仕事に就けなかったから」、「会社役員」は「自分で活躍できる場を広げたいから」との回答が3割を超えていた。
とあるように、本業で十分な収入を得られていない場合と、得られている場合では副業に対する動機づけが異なる傾向も見られました。
またパーソナル研究所「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2021年)においては
本業の職種別に副業内容(職種)をみると、本業が「医療・福祉・教育関連」「配送・物流」で、本業と同様の職種を選んでいる割合が5割超と高い。(61.3%)
次いで自営系(WEBサイト運営等)が25.8%、専門職種が25.3%である。
とされており、本業で身につけた知識や経験を活かせる副業を選ぶ傾向にあります。
これらの情報を踏まえれば
・医療、介護分野でも副業を選択する人は増えている
・およそ月5〜10万ほど収益が見込める、本業を活かせる副業を選択する人が多い
といった実情がわかります。

実際にどんな副業が人気なのか
副業の実情が見えてきたところで、実際にはどんな副業が人気なのかを見ていきましょう。
ケアきょう|ケアワーカー・介護職同士のコミュニティサイトによれば、介護職に人気の副業は
第1位:夜勤専従アルバイト
第2位:他の業界でのアルバイト
第3位:在宅ワーク
第4位:介護業界での日勤仕事
第5位:家事代行サービス
となっております。詳しい内容はこちら。
この第1位〜5位は先の副業の実情にも合っており、「まずは手早く稼げる手段を得る」といったところでしょう。
ただ注意しなければならないのが本業への影響で、介護・福祉の仕事は個人情報を多く含むものとなっています。業務上知り得た情報を外部に漏らさない守秘義務を厳守することが基本ですから、他施設で得た情報を本業の施設に持ち込むようなことがあってはいけません。
また同業種の場合、労働基準法における労働時間による問題も出てくるため、よく調べた上で選びましょう。
シェアリングエコノミー型の訪問介護・家事・生活支援サービス Crowd Care(クラウドケア)
もし首都圏で副業を始めたいなら、シェアリングエコノミー型の訪問介護・家事・生活支援サービスCrowd Care(クラウドケア)が選択肢に入ります。
こちらは主に首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で以下のサービスを提供しています。
①介護・介助手伝い
②通院付添、院内介助
③外出・余暇付き添い
④日中・夜間の見守り介助
⑤家事手伝い・家事代行
⑥その他生活支援
⑦認知症ケア(介護)
⑧障がい者ケア(支援)
⑨介護施設出張ケア
⑩旅行の付き添い・介護付き旅行(トラベルヘルプサービス)
※医療・看護に関わる行為、爪切り、マッサージ、運転代行など不可
これらのサービスを利用者として使うだけでなく、ヘルパー登録して働くこともできます。
働くヘルパーは、時給1,500円~2,000円(お仕事の条件によっては時給3,000円超も可能)。
しかも働く場所や日時を選べて、月1日1時間など個人の空き時間を活用し、働くことが可能です。
また他の仕事をしている方も副業として働けるため、副業の第一歩として取り組みやすいサービスとなっています。
具体的なサービス内容や報酬体系が知りたい方は、一度こちらをご覧になられるとよいでしょう。

家事代行サービスCaSy(カジー)
「介護業務ではなく家事代行をしてみたい」という方には、家事代行サービスCaSy(カジー)が候補に上がります。
こちらは30〜50代の女性に人気のサービスで、主に「お掃除」「お料理」を代行します。
【CaSyで行う「お掃除」「お料理」とは?】
・「お掃除」
お客様のお宅にある洗剤や掃除道具を使用し、水回りやお部屋の掃除・片付けなどを行う。
サービス提供エリアは関東圏を中心に、関西圏、東海・北陸、東北と広がりを見せています。
また週1回からのスキマ時間で働け、その上時給も基本1500円から、指名や昇給等によって最高時給が1850円にも登ります。
マニュアルや講習動画による研修、レベル別のオンライン勉強会、家事代行キャストのコミュニティもあってサポート体制も充実。未経験者でも安心して働くことができます。
さらに家事代行キャストの求人に応募後、30日以内に定期サービスの担当に慣れた場合にはデビューボーナスも用意されています。
家事代行サービスの内容や時給、ボーナス等を詳しく知りたい方は、一度こちらをご覧ください。

まとめ 〜介護・福祉職こそ自立を目指して副業を〜
今回は日本情勢を踏まえた上で介護・福祉職が副業を行う必要性、また副業の基礎知識と実情等について解説してきました。
副業は実際に始めるまでの準備が必要で、準備の時点で「まぁいいか」と挫折しがちです。
しかし自ら動き出さなければ毎日の生活が改善されることはなく、日に日に状況は悪化の一途をたどります。
特に2025年7月の参議院選挙以降は、国民の選択次第で物理的・経済的に「食うにも困る」状況に陥る可能性すらあり、これまで選挙に関心がなかったのだとしても今回ばかりは死活問題ですから、情報収集は欠かさない方が無難です。
そして、ここまで記事を読まれたあなたであれば、
「介護保険制度の変更まで待っていられる状況なのだろうか」
「介護報酬がプラスになるとも限らないのに、期待していいのか?」
「賃上げした分を税金で取られたら元も子もない」
といった考え方にシフトしていることでしょう。
現実問題として介護職が賃上げを求める限り増税は必須となり、介護・福祉職自らも「増税対象」である以上、お金の問題を国や政治家に任せていたら『貧しさループ』にはまるばかりです。
ぼんやりと「良さげな政策を打ち出してくれる政党・政治家を応援すればいい」と考えていた読み始めに比べて、今のあなたはより現実的に自分の収益や未来について考えるようになったのではないでしょうか。
あるいは介護保険制度や介護報酬に操られている自分や施設の姿がはっきり見えてきて、危機感を覚えた方もいるでしょう。
その感覚こそ『氣付き』で、あなたがこれから副業を始める上での強いモチベーションの「種」となるものです。あなたはそれまで当たり前だと思っていた現状が揺らぎ、ここから抜け出して自分の理想へと突き進むタイミングが『今』だと、理性が受け入れたのです。
そんなあなたがまず押さえるべき内容は
「介護の豊かさ」
「固定費の見直し」
「豊かになる介護士の5ステップ」
といった知識の補充と実践です。
介護・福祉職が自立してこそ社会が豊かになる
介護・福祉職としてお金の問題を解決するためには、「介護の豊かさとは何か」を知り、具体的な数値目標を設定した上で無駄な出費を抑えることになります。
副業について考えるのはサイフの穴を塞いでからであり、その上で自身の体調と人生の満足度とを天秤にかけて取り組むとよいでしょう。
そうして介護・福祉職として自分の業界だけでなく、広い視野が持てた時。
あなたは目の前の利用者が抱える背景について思いを馳せることができるようになります。
この社会を、社会保障費という安定した財源のない仕事で生き抜いた高齢者に対する思いを。
あるいは障害者が「はたらく」ことに対する思いを。
彼ら彼女らの生き様を「制度によって賃金が守れた介護・福祉職」という立場のままどこまで理解できるか。
それは自分で稼ぎ、少しでも自立しようとして初めて真に迫れるものだと言えます。

介護・福祉職が自立に向けて一歩先に進むことで、地域や社会の抱える問題に気付き、その問題を解決する手段を介護・福祉だけでなく副業による自サービスからも選択することもあるかもしれません。
そしてそれは、副業を始めずに自宅と施設を往来する日々からは生まれません。
介護・福祉職が一人ひとりが自分の、地域の、そして社会の課題と向き合ってこそもたらされる『社会福祉』なのです。
副業を行う理由は金銭的な生活苦からかもしれませんが、新たに仕事を行い自分の現状から抜け出し、視野を広げることで本業たる介護・福祉を多角的に捉えるようになります。
今回お伝えした内容を何度も読み返し、副業の準備から取り掛かることで介護保険制度や介護報酬、あるいは賃上げのために国そのものを窮地に追いやる選択をせずに済むかもしれません。
そうした自立した姿を見せるだけでも介護・福祉職の地位向上に貢献することができるでしょうし、人から選ばれる職業あるいは事業所になるでしょう。現状個人の尊重や自立支援を謳いながら事業所や職員が尊重されず、自立もできていない姿を周りの人々はよく見聞きしているのですから。
ただ、中には就業規則の関係で副業が行えない方もいらっしゃるかもしれません。
そうした方には金銭を得ないで自分の知識やスキル、人脈を広げる「パラレルキャリア」をお勧めします。
今回の話をまとめると
・社会保障費の原資の一つ、消費税の是非が問われる参議院選挙が行われている。
・その中で消費税増税の名目を与えるような動きを介護・福祉業界は行なっている。
・介護・福祉職個人は固定費の見直しや副業によってその動きに同調しなくても済む。
・副業を始める前に労働基準法や就業規則を見直し、副業が可能かを調べる。
・医療、介護で副業を行う人は多く、月5〜10万、本業での知見が活かせる仕事を選ぶ。
・その副業とは家事代行や夜勤専従アルバイト、登録ヘルパーなど。
・介護保険制度等が変わるのを待つより、自ら行動した方が早くて確実。
・介護・福祉職が副業を通じて自立に向かうと「あり方」が本質的となり、社会が豊かになる。
2025年の今、あらゆるヒト・モノ・コトが『本質・本音・本物』を問われる時代となりました。
介護・福祉職もまた自ら「個人の尊重」「自立」を実践し、介護・福祉サービスに説得力を持たせる時です。そしてその為には構造上依存的にならざるを得ない介護・福祉制度から片足だけでも抜け出せる努力をするべきです。
あなたが自らをより幸せで、豊かになるよう行動した時。
それが「人のしあわせ、ゆたかさ」たる『福祉』実践の真のスタートだと言えるのです。


介護ブログの他にも、介護ニュース等などを取り上げるnote、読書にまつわるアメーバブログを運営しております。
また僕が介護を考えるうえで参考になった書籍を紹介しますので、よかったら一度読んでみてください。
本からの学びは揺るぎない自信へとつながっていきます。
介護を自分の「感情」頼りにするのではなく、知識や経験に裏付けられた「事実」と併せて行うことで、介護はすべての人を豊かにしていくことができるのです。
一緒に学んでいきましょう。












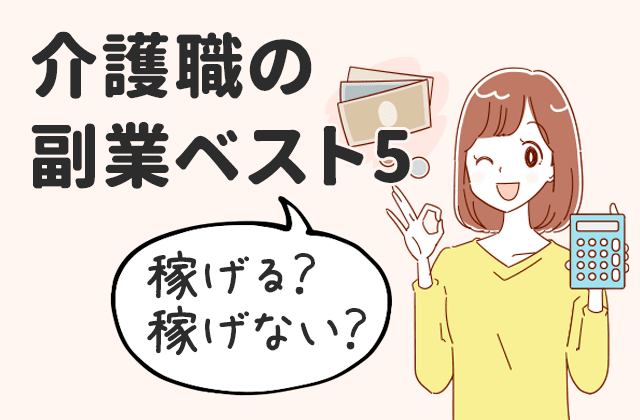







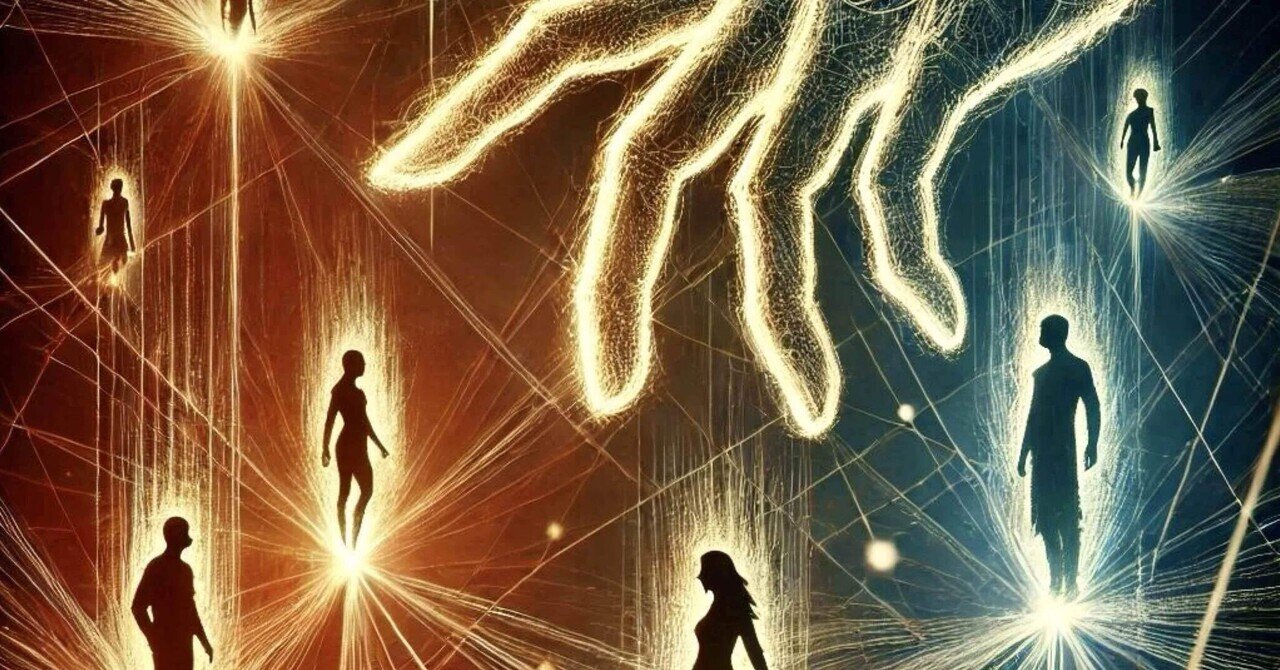




コメント